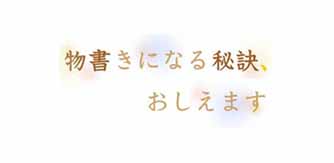|
|
| 5. 取るぞ新人賞、なんて若いぼくは張り切った |
| さて、時間はたっぷりあるし、まずは短編小説を書くぞ、と21歳のぼくは思ったのだった。 それには目標があって中央公論新人賞の応募締め切りが六月にあったからだった。 タイトルは「街の音」とした。 しかし、考えていたこととは裏腹に原稿はまったく書けなかった。 毎日、とりあえず、書いてみるのだけれど筆が萎縮してしまって、なにを書いているのかちっともわからない。 脳が過剰に反応しているのである。 今考えれば、「バカだなあ」とおもうけれど、しかし当時は真剣だった。 なにしろ、とっかかりがないのである。 赤瀬川さんの考現学教室に通ってはいたけれどでは赤瀬川さんが仕事を紹介してくれるか? といえばそんなことはない。 小説を書いて認められるには賞を取るしか道はないと思っていた。 しかし、筆はまったく進まなかった。 文章にはリズムがある。 それは人それぞれだけれどそのリズムがなければ、読み手はついてはこない。 うまい文章は淀みがないけれど下手なものは、読んでいると気分が悪くなる。 自分の書いているものは、明らかに下手でしかし、それでも必死になってとりあえず原稿を書き進めた。 一日中書いていると、誰にも会うこともない。 近所に友人がいるわけでもなく、そういう意味では一人だった。 次第に人に会うのが億劫になってきていた。 夜になると近所の酒屋で買ってきたウイスキーを飲む量が増えてきていた。 |