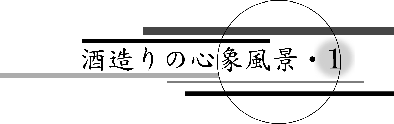「どうして一人で焼酎を造っているのか?」とよく訊かれる。
裸電球の下で朝から晩まで一人で働く姿を見て「アンタ孤独だねえ」と灯油を入れにきた燃料屋のおやじが呟くように言う。
人を雇う金がないわけじゃなし、社長にはもっと別の仕事があるだろう? というわけらしい。 造りに設計図は描かないけれど、大まかな筋はある。骨組みのようなものだ。
もともとは原稿書きの仕事をしていた。長い小説を書くにしても、短いコラムを書くにしても、流れがなければ話にならない。しかし、筋を決めてそれに添って書いても良いものになることは少ない。
「密度」という言葉が近いかもしれない。文章のなかに密度があって、それが濃かったり薄く流れたりしながら全体の味を決める。自分の考えた筋にこだわると「流れ」が消える。それが判ったのは最近のことだ。
焼酎造りも同じで造り方を決めても毎日同じことをしていると「判る」日がやってくる。
こうではなくて、ああしたほうが良いと思える日である。それは天の啓示のように突然くる。
人を使っているとそれは見えてこない。思い立ったらすぐに仕込み方を変えたいし、言葉にするのも、もどかしいくらい感覚的なものだ。説明しているあいだにその一瞬を逃してしまう。一人で造っている大きな要因はそこにある。
造りは秋口から始まって、翌年桜が散るころに終わる。暮れには出荷にも追われて慌ただしくなる。疲れが溜まって、云いようのない重いものが身体の動きを鈍くさせる。肩胛骨のあたりからジクジクとした嫌悪感に似た痛みが湧いてくる。それでも造りを続けているとやがてあっちの淵が見えてくる。神経が研ぎ澄まされて、仕込んでいるもろみの気持ちが判るようになる。
「もろみの気持ち」とはなにか?
つまりは「今、何をして欲しいのか?」が判るということだ。
暑いのか、寒いのか? もっと発酵したいのか? もう蒸留していも良いのか? 麦なら麦の、芋なら芋のもろみが囁く。「発酵して泡がたっているのを見るともろみが生きているのを実感する」という記事を読むけれど、そんなものではない。
もろみは友人でもなく家族でもない。自分でもないけれど、確かに息をしてそこに存在している。もろみと一緒にいるから誰と話さなくても寂しさは感じない。一人で原稿を書いているほうがずっと孤独である。
しかしそんなことを燃料屋のおやじに話しても伝わるわけはないし、すでに変人扱いされているところに拍車が掛かるだけのことだろう。
そうして出来た焼酎はとてもぼくが造ったとは思えない「味」がある。深く、そして喉を通ったあとで人に語りかける言葉を持っている。
あっちの淵が見えているときの自分は自分ではない。造りを終えるといつもそう思う。追い込まれて何かが生まれる。
いつか、もろみと一体になれなくなる日もくることだろう。そのときは終わりの季節だ。そう思っている。